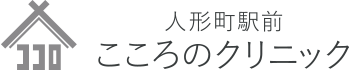こんにちわ ご無沙汰しています。
今回はリチウムが、アルツハイマー型認知症を予防する、という記事が日本でも出たのでそれについてちょっと書いてみます。というのも精神科で使用するリチウムは炭酸リチウムで使用するのに結構気をつかう薬で、安易につかうと命にかかわりかねないことになるためです。ですが調べるうちにそこまでナーバスにならなくてもよいのかなと思いました。とはいえ種類を間違えるとひどいことになるので使用には良く知っている医師の監督下で行ったほうが良いです。
リチウムが認知症を予防する
ネットニュースや新聞の常として分かりづらい、込み入ったものは省かれてしまう関係で記事のみを鵜呑みにするとよくないことが起きます。今回のニュースは題の通り単なるリチウムとしか書いていないのですが、実際の論文ではリチウムはリチウムでも「”オロチン酸”リチウムの有効性であるというものをマウスで確かめた」ということです。これ自体は正当な背景と理屈があって、アルツハイマー型認知症の予防(や治療)に新しい選択肢を与えるすごい研究です。ただこれを鵜呑みにした場合に”リチウム飲めばよいのか”となるとかなり危険なことが起きます。この点を知っておいてほしいと思います。
リチウムの種類
先ほどオロチン酸を強調したのはリチウム(リチウム塩)にも種類があるためです。
とりあえず、リチウムそのものについてですが、高校化学などでやるように水素の次に重い原子です。イオン化傾向が高く自然界には単体では存在しずらいです。ざっくりいうと非常に溶けやすく、溶けやすすぎて水に入れると燃え上がりながら溶けるくらい溶けやすいものです。なので自然では何かにくっついて存在します。また、性質としてはアルカリ金属の仲間なのでナトリウムに性質が近いです。要するに塩に似ている。人体でのふるまいもナトリウムに似ます。
最近はモバイルバッテリーや電気自動車などリチウム電池とかが話題で希少資源としていろいろ話題となりますが、それに使われるのは炭酸リチウムや水酸化リチウムで、よくあるニュースのように燃えやすいので、コバルト酸リチウムとかチタン酸リチウムとかにして安全に使えるようにすごく工夫して作っています。それでも燃えます。
医療において、よく使われるのは炭酸リチウムです。炭酸リチウムの錠剤が燃えたという話は聞きませんが、粉砕したりすると不安定で、中身が強アルカリ性になるので割らないほうが良いとされています。医療用のリチウムはそのほかに塩化リチウム、臭化リチウム、クエン酸リチウム、オロチン酸リチウムなどいろいろ検討されたようですが、結局副作用や製造コストなどから今はほとんどが炭酸リチウムになっています。
オロチン酸リチウム
今回の主役のオロチン酸リチウムですが、実は炭酸リチウムより良いんじゃないかとは50年ほど前から言われていて、その後も細々と研究が進んでいたようです。その研究の中心は双極性障害の躁病エピソードに対して、ということですが、付随して有効性なり危険性なりはちょくちょく研究されていました。
アルツハイマー型認知症に対しては、アルツハイマー型認知症において初期に細胞内のリチウム濃度が低下することが言われていて、それを補ったらよいんじゃないか、という点からリチウムの研究に向かったようです。これまでのリチウムの研究の中で、オロチン酸ナトリウムが一番脳に届きやすいからそれを使ったらよかった、というのがニュースの趣旨です。原理的には炭酸リチウムでもよさそうですが、芳しくなかったということもあったようです。
炭酸リチウムとオロチン酸リチウムの違い
炭酸リチウムは双極性障害の治療において重要な位置を占めます。昔から使われる薬で効果もよい。依存性や耐性などもなく、いわゆる薬漬けになりづらい薬です。それ以前に薬漬けにする方がまずいです。
これには中毒症状が知られています。(以下の項で記載しておきます)リチウムは一度蓄積すると体から排泄されるためには時間がかかります。症状が軽度であれば、ナトリウムを補充しつつ水分を大量に摂取することで対処しますが、重度となると透析などで積極的に排出する必要があります。そのため使用中は定期的に採血をして血中濃度や腎臓機能を確認し、ロキソニンなどの消炎鎮痛剤とも相性が悪いのでを避け、脱水などに注意して使わなければなりません。なので非常に気を使います。
一方でオロチン酸リチウムですが、北米では40年以上使われていますが、死亡例や深刻な副作用の報告はないようです。同じリチウムなのに違いがあるようです。一説にはオロチン酸リチウムの方が脳への取り込みがしやすく、炭酸リチウムに対して低用量でも治療効果が出るからと言われています。この違いがアルツハイマー型認知症の予防にも影響していたのかもしれません。
オロチン酸
そんな優秀そうなオロチン酸ですが、昔はビタミンB13とか呼ばれていたらしいですが、体内で合成されDNAの構成要素を作る途中の物質だったりいろいろいろいろ機能があるようです。また体内でミネラルキャリア(ミネラル分を体中に運ぶ物質)としての機能が優秀といわれ、なかなか細胞内に入りづらいミネラルイオンを取り込むためにも使われているようです。(たぶんこれが脳内に取り込まれやすいことにつながる)
改めて優秀なオロチン酸ですが、負の面もあります。ラットにおいてのこと。発がんを促すということが言われています。発癌性物質ではありません。ややこしいのですが、発がん性物質にさらされたラットにオロチン酸が高容量で投与されると発がんを促進するようです。幸い通常の用量ではこの影響は観察されていませんが気になるところです。
まとめ
そういう意味で比較的安全な様子のオロチン酸リチウムですが、いまだ研究が不十分なところもあります。特に長期使用におけるデータなどはよくわかっていません。リチウムなので腎臓や甲状腺、副甲状腺などにも影響がありそうとは思います。アルツハイマー型認知症の予防にどれだけの期間使用するかというのもありますが、安易に勧めるにはまだ個人的には抵抗があります。ご注意下さい。
※(炭酸)リチウムの毒性
急性中毒症状
軽度:吐き気、下痢、震え、脱力感、めまい
中等度:混乱、不明瞭な発語、協調運動障害
重度:痙攣、昏睡、死亡に至る場合も
長期使用による副作用
- 腎機能障害 :長期使用(特に10年以上)で腎臓の集合管機能が障害され、多尿、多飲症、腎臓の萎縮や間質性線維症を引き起こすことがあります
- 甲状腺機能低下症 :甲状腺ホルモンの合成と放出を減少させ、血清TSH(甲状腺刺激ホルモン)の上昇を引き起こします
- 副甲状腺機能亢進症:副甲状腺細胞のカルシウム感知メカニズムを阻害し、副甲状腺ホルモン(PTH)の放出を増加させます